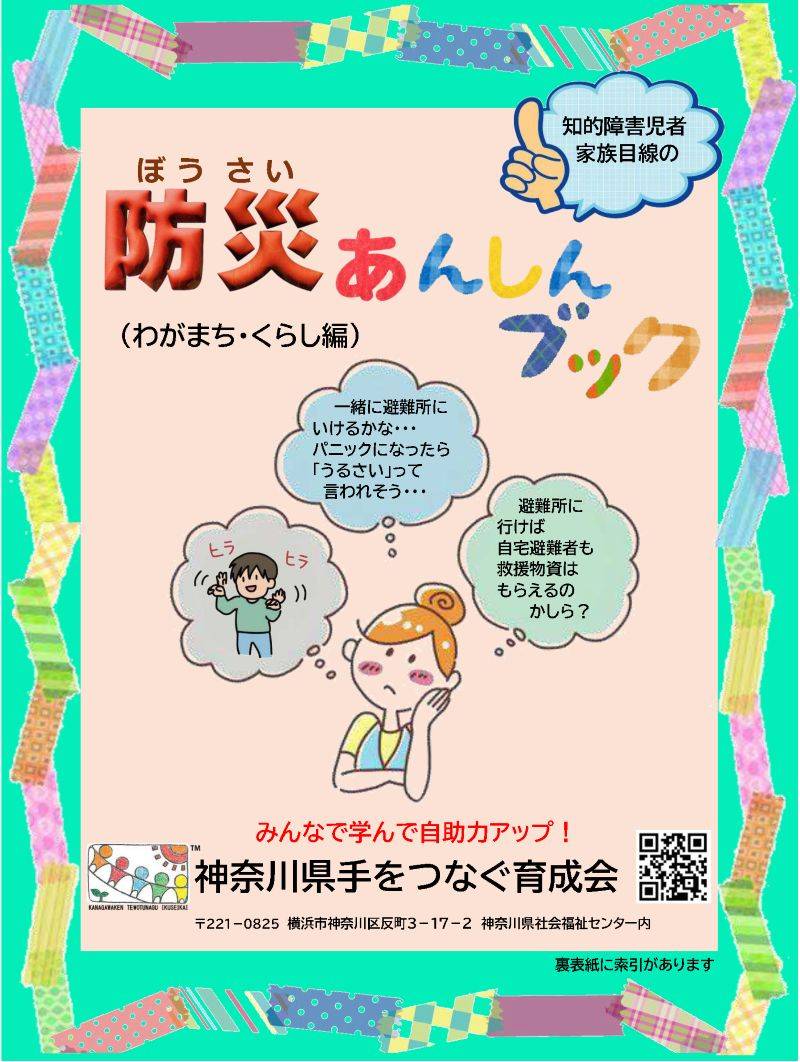被災地の暮らしを支える
「FamSKO」介護福祉士被災地派遣ガイドブック
- 分野 地域 / 社会貢献 /
- エリア全国 /
- 推進主体 その他の活動主体 /
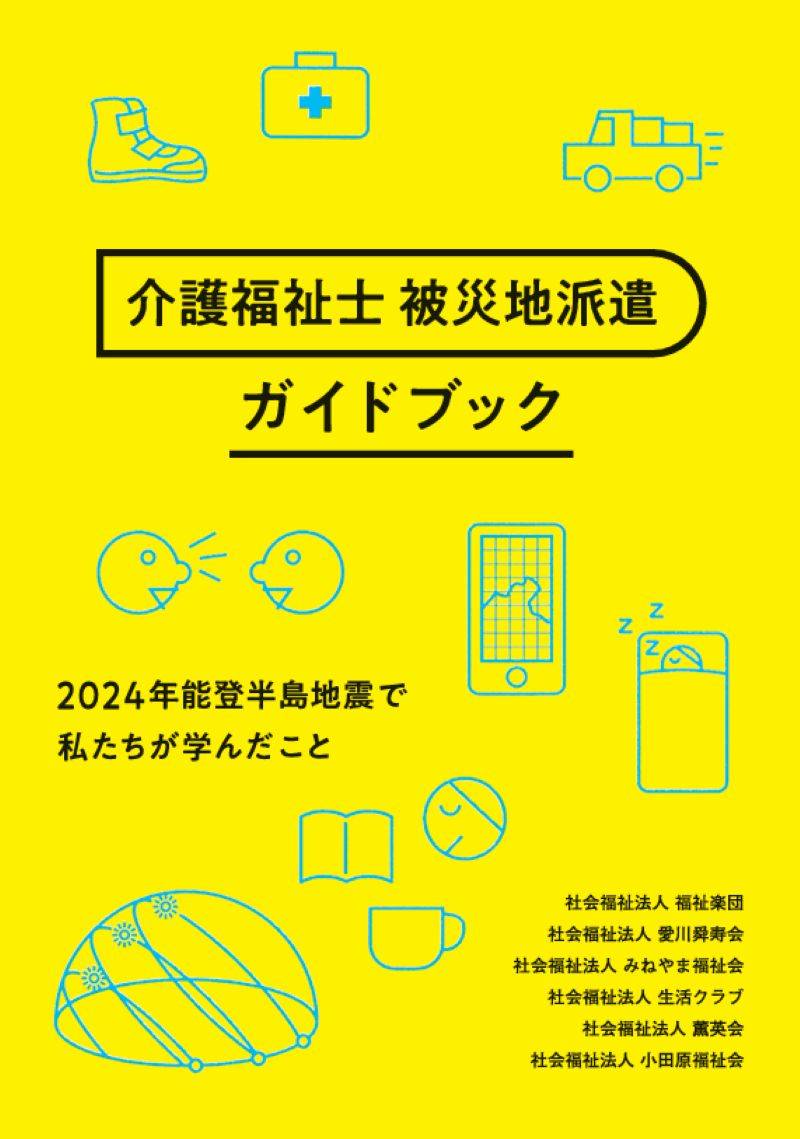
能登半島地震の初期に、6つの社会福祉法人の支援チーム「FamSKO」による介護福祉士の被災地派遣が行われました。「FamSKO」は法人の名前の頭文字を並べたもの。今回制作されたガイドブックや被災地での活動について「FamSKO」の県内2法人、愛川舜寿会理事長の馬場拓也さんと小田原福祉会・潤生園施設長の井口健一郎さんにお話を伺いました。
ガイドブックは、日々の支援活動をタイムラインで紹介しています。また支援にあたった12人の介護福祉士のインタビューから、被災地で活動する介護福祉士に必要なコンピテンシー(思考や行動特性)をまとめています。職員を派遣するバックオフィス側に求められるチェックリストを掲載しているのも特徴の一つです。
「被災地で活動したことをアーカイブしておくことが大事です。『介護福祉士を送り出すときのチェックリスト』には『自分の命を最優先に』『オーバーワークの防止』など基本的なことをあえて載せていますが、被災地の惨状を目の当たりにすると、通常と違う感覚になり、場に飲み込まれることがある。だからこそ基本的なことが大事になってきます」と話す馬場さん。
介護のインフラを止めない
能登半島地震では、上下水道や道路などのインフラの崩壊がありましたが、介護のインフラも危機的でした。「現地の介護職員は『利用者が待っている。行かなきゃ』となる。しかし、家が倒壊し子どもが不安定になり『ママ行かないで』としがみついて泣かれる中でそれは厳しい。発災直後は被災した職員は勤務できないので、やはり人手が必要です。しかし全国的な派遣の仕組みが開始されるには時間がかかります。でも、小さい支援組織であれば機敏な動きができる。だから『FamSKO』がその間をつなぎました」と馬場さんは言います。
介護福祉士のコンピテンシー
福祉避難所であっても求められる専門性は変わりません。ですが、12人のインタビューでは、普段の現場以上に、ケアの専門性を先鋭化していたことが分かりました。
「私も現地の福祉避難所に1週間ほど入りましたが、避難者が在宅に戻れるよう生活を整えていこうと、自立支援に取り組んできました。一方、大きな避難所ではベルトコンベア式のようなケアという状況もあって、避難者のADLがみるみる下がってしまったという話も聞いています。そうなると、生活の整え方が違ったのかもしれない」と井口さんは言います。
馬場さんは「言ってしまえば、ケアは誰にでもできるわけです。しかし、ケアにはより深い専門性、コンピテンシーのようなものがある。ケアは機能を果たすだけのものか、生活の質を問うか」。それによって目標も支援計画も大きく変わってくると言います。
被災地での支援の広がり
派遣された介護福祉士にはどんな影響があったのでしょうか。
「介護って、介護を通して社会をケアしていく、そういう仕事だと思うのですが、普段は日常のルーティンになっている部分もあります。被災地から戻って『人間って困っているときに、みんな助け合おうとする生き物なんだ』と言った職員がいましたが、感性の扉がパカッと開いたのでは?被災地の経験は、人を支える仕事をもう一度見つめなおす貴重な機会だと思います」と馬場さんは語ります。


お話を伺った馬場さんと井口さん
井口さんは言います。「『義をみてせざるは勇無きなり』と言いますが、本当に困っている人がいるとき、社会福祉法人であれば自らが駆けつけよう、支援に行こうとなるはず。その一歩が踏み出せるかどうか。それが社会福祉法人の一つの資質なのだろうと思います」
ガイドブックでは、未来につなげるための提言もしています。ここでまとめられた被災地支援の経験の蓄積と提言は、次の災害への大きな備えになることが期待されます。(企画課)